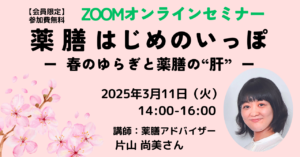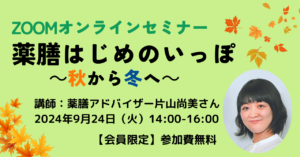こんにちは。フォトグラファーのむーちょこと、武藤奈緒美です。
今年の3月末、代々木の古い雑居ビルに仕事の拠点を置いて丸10年が経ちました。ここにたどり着くまでの8年間は先輩フォトグラファーの事務所に家賃3分の1で厄介になっていたことを思うと、この10年家賃を払うの頑張った!とさすがに自分を労う気持ちでいっぱいになりました。
その雑居ビルは私のようにそこを拠点にしているクリエイターがたくさんいて、とりわけ隣りの隣りをアトリエにしているスペイン人のNとは同業者のよしみでほぼ毎日挨拶をかわし、時々立ち話もする(もちろん日本語で)距離感です。去年の12月、私が旅仕事で2週間不在にしていたときには、「長く留守だったようだけど、何かあった?大丈夫だった?」とわざわざ私の部屋を訪ねて言葉をかけてくれ、それがやたら心に響いて、素敵なご近所さんに恵まれたことをありがたく思ったのでした。

2018年11月、地中海マルタ島にて武藤奈緒美撮影。以下の写真も同様
そのNが原宿のギャラリーで写真展をやるから時間があったら寄って、と写真展の案内状をドアに挟んでいきました。そこには多分日本じゃないどこかで撮った壁のブルーがきれいな部屋の写真が印刷されており、一週間ほどの会期で足を運べそうなのが最終日の夕方だったので、その日仕事を片付けた足で大急ぎで原宿に向かいました。
大きなガラスばりのギャラリーは通りから中がよく見えて、写真作品たちが整然と横並びにではなく、私から見るととても自由奔放に、おそらくそれはNの理想の配列として展示されていました。
受付のところにいたNに「写真展開催おめでとう」と言葉をかけ、ひとつひとつの写真をゆっくりとまずは時計回りに順繰りに見ていきました。それらはNが数年前にキューバを旅して撮った写真たちで、時計回りのちょうど12時のあたりにくだんの案内状に使われていた写真が大きく引き伸ばして展示されていて、そこはまさにこの写真展会場の要のような場所になっていました。

作品全体の印象は、三脚を構えタイミングをひたすら待ってようやくシャッターを切った、というんではなく、反射的に撮った次の瞬間にはその光景自体が消えてしまっていそうな儚さが漂っていました。
そういうふうに感じさせる撮り方がNのふだんの作風なのか、たまたま今回展示した写真ではそうなのか、これまでのNの作品をつぶさに見たわけではないからわかりませんが、ただこの写真展に関してはそういう印象を抱いたのです。
時計回りの次は反時計回りして、12時のところにある写真の前で立ち止まってじっと眺め、次は気に留まった写真を順繰りに見る。私だったらこっちの写真を案内状に使いたいなと思う写真があったので、ひとしきり見つくしたのちNに「あの写真を写真展の案内状に選んだわけは?」と尋ねたところ、ひとこと「feeling」と返ってきました。それはふだん私が口にする「フィーリング」とはまるで違うイントネーションの「feeling」でした。

今回はfeelingであの写真を選んだけれど、別の機会に同じテーマで写真展をやるとしたらそのときのfeelingで違う写真を選ぶかもしれないし、展示する写真も並べ方も全然違うものになると思う。写真の色も、今回はこういう色にしたけれど、別の機会だったら違う色がいいと思うかもしれない。そのときのfeelingがすべてだ。
そういうようなことをNは、ややおぼつかない日本語ながらも確信に満ちた眼差しで語ってくれました。
なんて自由なのだろうと感激した直後、そうだ、そうなんだ、それでいいんだ、という気持ちがふつふつと湧き起こって、私もこれからはfeelingを何よりも優先させようじゃあないか!と一気にNの考えに魅了されました。
でも待てよ。思えば、私自身シャッターをどこで切るかはそのときのfeelingにしたがっているわけで、私もfeelingのしもべに相違ないのだ。一点違っているのは、Nはそのfeelingをすみずみにまで行き渡らせ、一方私は無自覚だったということ。無自覚だからせっかくのfeelingをこねくりまわして駄目にしちゃうこともこれまであったんじゃないかと思う。そこに気付いた。これは私にとってのブレイクスルーというやつではなかろうか。
新型コロナウィルスの感染状況がもう少し落ち着いたら、代々木に拠点を移して丸10年記念の写真展をやりたいと考えている。そのタイミングが来たらそのときのfeelingにすべてを委ねてみよう。