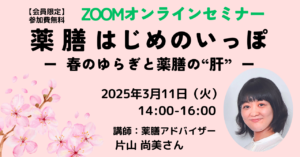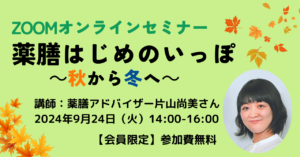「マツコの知らない世界」で紹介された超人気ニット帽
みなさん、こんにちは! 常識に捉われないアイデアと大胆な行動力を持つ「世界を明るく照らす稀な人」を追いかけて東奔西走、稀人ハンターの川内です。
最近の東京は、少しずつ暖かくなってきました。とはいえまだ風は冷たく、特に朝晩は手袋やマフラー、ニット帽は欠かせません(編集部注:本記事は3月に書かれたものです)。ちなみに僕はニット帽が好きでたくさん持っているのですが、以前からずーっと気になっているニット帽があります。
その名も、「遮光器土偶(しゃこうきどぐう)ニット帽」。
.jpg)
カラーバリエーションおある遮光器土偶ニット帽(提供:小牧野遺跡保存活用協議会)
へ? と思った方も多いと思うので、簡単に紹介しましょう。このニット帽は、青森市小牧野遺跡保護センター(縄文の学び舎・小牧野館)が開発したオリジナル商品。モデルになっているのが、1887(明治20)年、青森県つがる市にある亀ヶ岡遺跡で発掘された、メガネをかけているような姿の土偶です。そのメガネが、北方民族のイヌイットが雪中の光の照り返しを避けるために着用した「遮光器」に似ていることから、「遮光器土偶」と名付けられました。
遮光器土偶の頭部には、「王冠状突起」と呼ばれる複雑な装飾が施されており、遮光器土偶ニット帽は、その「王冠状突起」を手編みで再現しています。今年2月7日に人気番組「マツコの知らない世界」に出演したミュージアムグッズ愛好家の大澤夏美さんが紹介していたので、番組を観た方は、ご存じでしょう。
実はこの遮光器土偶ニット帽、とんでもない人気で、滅多に手に入らない激レア商品なんです。そして、縄文の学び舎・小牧野館はほかにも遮光器土偶の「遮光器」部分を再現した木製のメガネや遮光器土偶形のこけしとけん玉を合わせた「シャコケン」など個性的なオリジナルグッズを次々と開発しています。その舞台裏では、意外なキャリアを持つ館長が奮闘していました。ということで、今回は縄文の学び舎・小牧野館を紹介します。
青森に帰郷した元ミュージシャン

縄文の学び舎・小牧野館の館長、竹中富之さん
縄文の学び舎・小牧野館の館長は、竹中富之さん。オリジナルグッズのプロデュースを手掛け、「縄文」界隈のヒットメーカーとして注目を集める彼のキャリアは、意外なものです。プロのミュージシャンとしてバンドのボーカルを務め、過去には聖飢魔IIと同じ事務所からCDも出しているのです。
しかし2003年、プロミュージシャンとして大成することができず、バンドも解散。これからどうしようかと悩んだ竹中さんは、「音楽に関係ある仕事がしたい」と考えました。それから縁あって、38歳の時、渋谷にある音楽系ミュージアムの責任者に就きます。ミュージアムの運営についてまったくの素人でしたが、徐々にアイデアマンとしての才覚を発揮し、「ミュージアムの運営は面白い!」と手ごたえを得ていました。
ところが2010年、両親の体調が悪化したこともあり、故郷の青森市にUターンすることに。仕事のあてがなかったため、「自分で仕事を作ろう」と、地元で世界のカルチャーを発信することを目的にエスニック雑貨のショップを始めました。
それからひとりでインド、ネパール、タイ、メキシコなどを旅行し、気に入った雑貨を仕入れて自分のショップで売る生活がスタート。このとき、商売人としての目が養われたそうです。
「現地で商品を見定めながら、これをいくらで販売したら売れるだろう?って考えるじゃないですか。この商品はもっと改良できるんじゃないかっていうのもすごく気にするタイプです」
ショップでは、アフリカの太鼓「ジェンベ」も仕入れて販売していました。それがきっかけで、地元の仲間たちとジェンベのチームを結成。すると、そのうちに「遺跡で演奏してほしい」というオファーがくるようになりました。
なぜ遺跡で? 青森は遮光器土偶が出土した亀ヶ岡遺跡、縄文遺跡として日本最大級の三内丸山遺跡など約4700カ所の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が確認されていて、遺跡関連のイベントも多いのです。皮と木で作られた原始的なジェンベは、遺跡との相性もよかったのでしょう。もともと遺跡に興味がなかった竹中さんも、徐々に遺跡に関心を抱くようになりました。
カート・コバーンがきっかけで生まれたメガネ

廃校を利用した縄文の学び舎・小牧野館
雑貨ショップを開いて3年目、環状列石(ストーンサークル)がある小牧野遺跡の出土品の展示や保管に加えて、縄文遺跡全般の情報発信などの拠点として縄文の学び舎・小牧野館をリニューアルするという話が立ち上がりました。その時、かつて東京でミュージアムの責任者を務めていたキャリアを買われて「有識者会議に参加してほしい」と依頼をうけて参加。
完成が近づいた頃、青森市が指定管理者制度を導入することがわかりました。指定管理者制度とは、公共の施設の管理・運営に民間のノウハウを活用しようという考えから、行政が民間の事業者を含めた幅広い団体に管理・運営をゆだねる制度です。
指定管理者の募集要項を見ると、必ずしも考古学や縄文文化の専門家である必要はありませんでした。その時、「縄文文化と言われても、かつての自分のように特に興味がない人のほうが多いはず。そのハードルを下げて、もっと身近なものにしたい」と考えた竹中さんは、仲間に声をかけて「一般社団法人 小牧野遺跡保存活用協議会」を結成し、指定管理者に立候補。
手を挙げた3者のなかからトップの評価を得て選出され、2015年5月、「縄文の学び舎・小牧野館」のオープンと同時に館長に就任しました。
仕事を始めて驚いたのは、さまざまなグッズを販売するミュージアムショップを設置するのに「目的外使用料」という場所代を求められること。視点を変えると、ミュージアムショップのグッズが場所代を上回れば、その売り上げは協議会の収入アップにつながります。
「売れるグッズを作るしかない!」と燃え上がった竹中さんは、小牧野遺跡の環状列石の配置をポップにデザインしたマスキングテープ、小牧野遺跡のロゴマーク入りタイダイTシャツを開発。2019年には、遮光器土偶メガネをリリースします。開発のヒントになったのは、竹中さんが好きなアメリカのバンド、ニルヴァーナ。上京した際、カリスマボーカルのカート・コバーンがよくかけていたようなサングラスを見かけた瞬間、「遮光器土偶に似てる!」と開発を思い立ったそうです。
ヤフオク出品で驚愕の値段に

誰が着けても笑える遮光器土偶メガネ
竹中さんを中心とした小牧野館チームが生み出した最大のヒット商品が、冒頭に記した遮光器土偶ニット帽。これは、竹中さんとスタッフが「こんなニット帽があったらいいよね」と雑談をしていたところ、後日、その話を聞いた外部の女性(仮にAさんとする)が「1回、編んでみようか」と言ってきたことから開発が始まりました。
4回の試作を重ねた末、見事に「王冠状突起」を表現したニット帽が完成。これは話題になると確信した竹中さんは、ミュージアムショップで5個だけ販売し、残りはカラー指定もできるメールでの受注生産としました。
その反響は、想像をはるかに超えていました。2020年1月25日、1つ4400円で50個発売したところ、SNSで話題になったのがきっかけで、約100通のメールが届いたのです。この人気は収まることを知らず、2020年11月に発売した第2弾(約50個)では、1000人超が応募。
2021年12月に発売した第3弾(60個)では、「ニット帽の価格が安すぎるせいで、需給のバランスが崩れている」という指摘や「公平性、透明性の高い販売方法を」という声があったため、試験的にヤフオクを利用しました。すると、6600円でスタートした価格が2日目には2万円、3日目には4万円を超え、電話、メールで「この金額では手が出せない、なんとかならないか」と問い合わせも多く届いたため、最初のひとつで出品を打ち切り。
残りの59個はひとつ9900円、ハガキでの抽選という形で購入希望の受付を始めたところ、1000通を超える応募があり、竹中さんとスタッフ、そして今もひとりで編み続けているAさんは仰天したそうです。
販売個数を増やさない理由
周囲からさまざまな意見が寄せられるなかで、最も多いのは「そんなに人気があるなら、販売個数を増やしたら?」。もちろん、増産すれば協議会の収入が増えますが、竹中さんは個数を増やさないことに決めました。それは、Aさんから「私がやり切ります」という言葉を聞いたからです。
「たくさん売ればその分儲かりますけど、僕らがグッズを作るいちばんの目的はそこじゃない。それに、エスニック雑貨店をしていた時、なによりも現地の人との気持ちのいい取引を重視していました。今回も、まだ商品になるかわからない段階から付き合ってくれた作り手の気持ちを大切にしようと思ったんです。だから、Aさんにはいつまでに何個作ってほしいという依頼もしません。自分のペースで、できる範囲で作ってくださいと伝えています」
僕が取材に行ったのは、2022年1月。竹中さんの方針は今も変わっていないようで、昨年12月に始めたハガキによる抽選販売も、用意したのは65個でした。青森経済新聞によると、応募開始2日で110通を超えるハガキが届いたそうです(【青森・小牧野遺跡「遮光器土偶ニット帽」に新色 今年も抽選販売】/2022.12.08)。
あまりに狭き門なので僕はまだ応募したことがないのですが、遮光器土偶ニット帽、いつか手に入れたいという野心を燃やしています。
ちなみに、2021年に世界遺産に登録されて盛り上がる「北海道・北東北の縄文遺跡群」のなかでも日本最大級の縄文集落跡、青森市の三内丸山遺跡から縄文の学び舎・小牧野館までは、車で15分程度。小牧野遺跡だけでなく、縄文遺跡全般を紹介しているので、常設展示もかなりの見ごたえがあります。ミュージアムショップには遮光器土偶ニット帽以外のオリジナルグッズも売られていて、お土産にバッチリ。青森市に足を運んだ際には、ぜひ立ち寄ってみてください!

小牧野館から少し離れた場所にある小牧野遺跡
稀人ハンターの旅はまだまだ続く――。