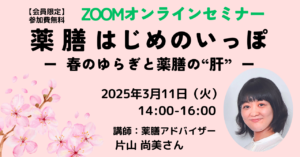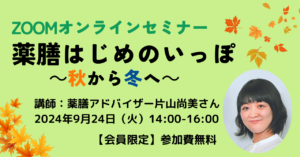フォトグラファーのむーちょこと、武藤奈緒美です。
盛岡で「短歌甲子園」の取材をしてきました。
正式名称は全国高校生短歌大会といいます。「甲子園」と呼ぶ方が青春味がぐんと増すし、短歌を詠むという個人的な営みをどうやって競技化するのか俄然興味が湧きます。

かく言う私は、就職活動の最中にそのしんどさを五・七・五・七・七の三十一文字(みそひともじ)に託してうさ晴らしをしていた時期があります。愚痴を言ったら止まらなくなりそうな状況に、その気持ちを引っ張りたくなくて三十一文字でケリをつけることにする・・・当時そんなことを考えていたのだったか。
愛猫を喪ったときにも、その老いと死を三十一文字に託しました。おしまいに向かいつつある彼女との時間、彼女の居る風景を完結に三十一文字に収めておきたかった、いや固定したかったのか。文章だと気持ちがとめどなくあふれてそこに埋没してしまいそうだったから。
短歌を詠むのが習慣なわけでもないのに、なんでか時々三十一文字、五・七・五・七・七のリズムに収めようと思うときがある。いや、心情がそこにのるというか、ぴたりとはまるというか。就職活動のときも猫の晩年のときもそうでした。私の場合は収拾のつかなくなった感情を整理するときに五・七・五・七・七がしっくりくるのかもしれません。

「短歌甲子園」は歌人・石川啄木の故郷である盛岡が発祥で、市が盛岡ブランド開発を目指して始めた事業のひとつとのこと。ほかに「短歌のまち もりおか」推進のために「短歌ボックス」を市内各所に配置しています。取材で訪れた渋民駅で実際このボックスを見かけました。短歌が書かれているであろう白い紙が何枚も入っていて、盛岡の人にとって啄木や短歌は日々の暮らしの中に当たり前のように存在している様子。
取材先は短歌甲子園に出場経験のある盛岡市内の高校の文芸部でした。予想に反して男子が多く、この時期の男子はたとえ何かしらの創作を行っていてもそれを表に出すことは照れくさいんじゃないかなどと安易に思っていた私は、いい意味で裏切られました。そもそも女子高上がりの私は今時分の男子高校生どころか当時の男子高校生の有り様も知らないんだった・・・。
短歌甲子園ではお題として漢字1字が掲示され、それを詠み込んだ歌を制限時間内に作ります。「題詠」というんだそうで、さらには石川啄木の短歌作品の形式に則って3行書きで表現することが決められています。団体戦と個人戦があり、団体戦では先鋒・中堅・大将戦を行い、審査員のポイント数で勝敗が決定、先に2勝したチームが勝利・・・剣道の試合みたいで、あくまで競技であることが伺えます。

取材に入った日も漢字1字がお題に出され、各自スマートフォンを片手にもう一方の手でシャープペンシルを握り、俯いて忙しなく手を動かすこと20分。その様子を私はあちこち動き回って撮影しました。部室の窓を背にした彼らの背後では木々の緑が揺れ、逆光の中で言葉と格闘する制服姿が美しかった。
何も事情を知らないで見たら「またそんなスマホばっかり見て・・・」な風景ですが、彼らは無数の言葉の中から自分の創作にぴたりと添ってくれる言葉を果てしないインターネットの世界から探し出そうと躍起なのです。今まさに自分の言葉の領域を広げているさなか。

制限時間もおしまいに近づくと、片方の手指を握ったり開いたりする様子があちこちで見られ、三十一文字を数えているのがわかりました。頭を抱えたり、目を閉じたまま上を見上げたり、歌を詠む姿はそれぞれで、今彼らの頭の中はたくさんの言葉とそれがもたらす風景がぐるぐる渦巻いているのでしょうか。
20分が経ち、各自短冊状に切った紙に一首したため、正面のホワイトボードにマグネットで留め、その前に横並びに立ちました。誰がどれを詠んだのかは伏せ(文字で分かるけどねと言っていましたが)、その日のリーダーが一首ずつ詠み上げ各自好きな歌に手を挙げ、順々に講評していきます。
この言葉がどの言葉に掛かるかによって2つの意味に取れるよね、とか、この言葉に色を感じるしそれによって気持ちが伝わる、とか、一首一首をひとりひとりが丁寧に細やかに見つめ思考し理解しようとしているのが背中越しでも十分伝わってきて、ああいい時間だと私はしみじみと思いました。言葉に対する誠実さとその言葉を用いた作者に対しての誠実さと。真摯に向き合うことのかっこよさをこれでもかと背中が語ってくれました。
「いや、こんな経験、ないよ、まだもちろん!」と自分の歌を講評された後に慌てるようにして取り繕った男子学生の歌はちょっと背伸びしたような出来事を詠んでいて、憧れを詠んだのかそれともいつか自分にもそういうことが訪れるだろうという未来形を詠んだのか。

昔ながらの短歌という形式を十代の彼らが率先して表現方法に選んでいることが私には新鮮であったけれど、彼らはその価値というか意義をちゃんと感じ取って歌を詠んでいるんじゃないか。表現を狭めているのはなんだ自分じゃないか。取材を振り返ってそんなことを思いました。
啄木と彼らに導かれ、私も一首。
十代の歌詠みたちの指先に
宿っては過ぎる
幾多の言葉