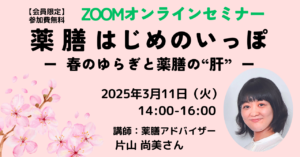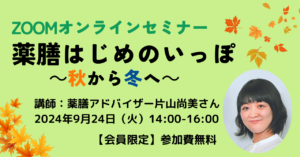残暑お見舞い申し上げます。フォトグラファーのむーちょこと、武藤奈緒美です。
これを書いているのは暑さのピークが去ったかな・・・とようやく感じ始めた8月下旬。
新型コロナウイルスが再び猛威を奮う第七波のさなか。ここにきて身近に接している人たちにも感染者が出てきて、わたしも抗原検査を受けました。なんらかの症状があって検査したわけではないのですが、判明するまでの間まさかあんなに緊張するとは・・・な体験でした(陰性でした)。今しばらく油断せずに過ごそうと思います。

春のおしまいの頃に撮影で関わった企画が少し前にかたち・・・「日本の台所100年 キッチンから愛をこめて」(平凡社)になりました。
その中でわたしは「作家たちの愛した台所」というページを担当しており、安西水丸さん(イラストレイター)・石津謙介さん(ファッションデザイナー)・宮脇檀さん(建築家)それぞれが生前馴れ親しんだ台所を撮影しています。
亡くなってもう何年も経つ方たちなので、取材に伺ってお目にかかるご遺族は哀しみが前面に立つよりかは懐かしみがまさるご様子で、時におもしろおかしいエピソードを挟み込みながら台所や食にまつわる故人の思い出をお話しになり、それを聞きながら目の前の台所や愛用していた台所道具を眺めると、そこに故人の気配が宿っているような、存在感というかたちがそこにたたずまっているような心地を覚えました。そしてわたしはその感触を写真にトレースすることにひたすら意識を集中させました。

お三方の中で唯一私がお目にかかったことがあるのは安西水丸さんで、お亡くなりになる数ヶ月前に2度、アトリエとオフィスで撮影する機会がありました。
ご遺族の語りというのはなんとも不思議なもので、生前のその人を存じ上げないこちら側に、その人の何かしら・・・漠としているのだけれどたしかにその人であるというような・・・を浸透させてくる力があるようです。気付くと、語られる思い出の場面に私自身も遭遇していた気になっていました。
また、世間的にどれだけ著名な方でも、遺族の語りの中では著名さは薄れ、その家族の中での最もシンプルな役割・・・父だとか祖父だとか伴侶だとか・・・として語られる。当たり前といえば至極当たり前のことなのですが、ああそういうものなんだなと実感もしました。

故人が馴れ親しんだ台所は、そのまま保存されていたわけではなく、その後も家族によって使われてきたわけだから場の空気は上書きされているはずなのに、「そうそう、よくこの鍋でカレーを作ってこの椅子に座って台所で食べていたんですよ」と遺族が語り、その椅子を「こんな具合でしたか?」と尋ねながら配置し鍋や器を置いてみると、そこに在りし日の背中が見えてくる。
「父はよくこのスープを作ってくれました」と娘さんが窓辺のテーブルに再現したスープをよそった器とスプーンを置く。障子越しの光が柔らかくテーブルに注いでいる。光自体は当時も今もさほど違うものではないだろうなと思うと、台所からテーブルまで器を運んでくる在りし日の動線が感じられる。

語りに導かれてそこに姿を感じながら撮る。居るように撮る。
今は記念館になっている誰それが住んでいた家だとか、ホテル内に再現された誰それが執筆した部屋だとかをこれまで撮る機会がありましたが、今回の台所の撮影はそれらの時とは全く違った感触で、じゃあどう違うのかと言うと、前者はあくまで観察者の目線、後者は遺族の語りによってその場に紐づけられたような、その場にくるっと包み込まれたような、場の一員みたいな心地でした。
殊更にそれを感じたのは宮脇檀さんの台所を訪れた時で、語ってくれたのが娘さんだからだろうと思います。私の父は80目前にしてピンピンしていますが、自分も娘である分彼女の語りにシンクロするところがあって、彼女の父を喪くすという経験が自分事になって胸がきゅうっとなりました。
今回の写真の上がりを見て、同様に場を撮影したこれまでの写真となんだかちょっと趣きが違う気がしています。ふくらみのある空間が撮れたような・・・そこに宿る物語も含めて是非お手にとって見ていただきたい一冊です。