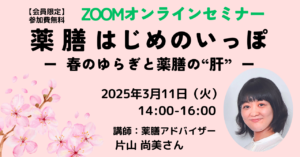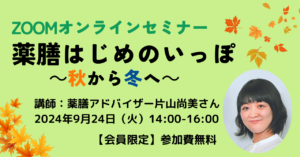お久しぶりです。フォトグラファーのむーちょこと、武藤奈緒美です。
前回の更新から随分時間が空いてしまいました。
3月22日にスタートした写真展「ポートレイト2020-2022」を4月30日に終え一段落・・・のつもりがすでに5月末。
新型コロナウィルス蔓延の3年間ですっかりスロウモードが定着した模様です(言い訳ですね・・・)。ここから盛り返していくためにも写真展の振り返りをしておきたいと思います。

4年ぶりの個展開催でした。定期的に開催してきたわけではありませんが、前回が2019年、その前が2016年で、展示できそうなネタがまとまったら開催するという形を続けてきました。
今回は、2020年から2022年の間に撮影依頼をいただいた落語家さんのポートレイトを、撮影日順に前後期に分けて展示しました。
この展示に関わっていただいた落語家さんの人数は50を越えます。
落語家の数は東京だけでも600人を超えるとか。なのでまだまだ追っかけきれていませんが、それでも世間が新型コロナウィルス蔓延で停滞していた期間に、しかももっとも打撃をくらったといっても過言ではない彼らから撮影の依頼をいただいたのはありがたく嬉しいことでした。その気持ちも込めたかった。

ふだんレンズ越しに対象を見る側の私は、この個展期間中、自分の撮った写真が展示という形式の中でどう見えるのか、他者がそれらをどう見るのかに関心がありました。
会場は去年夏にオープンしたカフェギャラリーで、駅からそう遠くないとはいえ繁華街ではなく、通りすがりの人が訪れるというわけでもありません。足を運んでくれたのは、落語ファン、写真が展示されている落語家のファン、ギャラリーのお客さん、わたしの友人知人クライアント、といったところでしょうか。準備が遅れDMを送りきれなかったのでお知らせはSNS頼り、めっきり使わなくなったFacebookまで動員して宣伝をしました。落語家さんも落語ファンもTwitter利用者が多いので、そこでの宣伝は毎日おこない、たびたび拡散もしていただきました。結果、はじめましての方に多数お越しいただきました。
撮影のない日あるいは撮影が早く終わる日は会場に赴き、いらした方とできるだけお話しました。ひとりでお越しになる方が多く、どの写真が好きか、どういう部分に惹かれるかなど夢中に楽しげに感想や想いを語ってくださって、自分が撮った落語家さんの写真がどう受け止められているかをじかに知ることができました。
依頼をいただいて撮影しているとはいえ、私自身落語ファンですし、撮っているときは「この人の魅力をなんとか引き出したい!」と必死ですから、そうして撮った写真を見て喜んでもらえるのは、(殊更低くも高くもないとはいえ)自己肯定感が増すし、まだまだ写真を撮っていくぞと何度も心に期することができました。

落語家さんにも多数お越しいただきました。写真が展示されている方のみならず、毎月撮影に入っている渋谷らくごに出演している方や過去に撮影したことのある方も。会期後半になると駆け込み需要も手伝って、対応が追い付かなくなるほど多くの方にお越しいただきました。どうやら楽しんでいただけたようで、ただひたすらに安堵でした。
過去にも落語家さんの写真展をしたことがあります。それは月刊演芸誌「東京かわら版」の創刊40周年記念の企画展示で、長年表紙巻頭の撮影で関わらせてもらっているわたしも写真展という形で企画に混ぜてもらいました。
このときは大きな黒い板にポートレイト写真を直貼りしての展示でしたが、今回の写真展ではひとりずつ額装して展示しました。
黒いフレームに白いマットを合わせ横並びで展示してみて気づいたことは、額装すると写っているひとりひとりの空間というか世界というかが完結して見えるということ。隣の人(写真)と干渉しないというか、独立しているというか。落語家というひとり商売のそのひとり性の部分がとても際立って感じられたのです。ああ、この人は自分の看板を下げて、自分を恃んで、世間と対峙しているのだなと。

好きで選んだとはいえ、厳しい道です。その厳しい道をゆく人たちはおおむね軽妙で厳しいことなど匂わせず、明るい存在然としています。新型コロナウィルスの影響で仕事が止まってもいい表情でカメラの前に居続けてくれました。同じく仕事が止まった私にとって、撮影依頼とともに見せてくれるそうした表情はあの時期の光でした。なんとかやり過ごしたあの時期、気持ちが落ちないように不安にならないように自分で自分をフォローしまくった時期の光でした。写真展をやることで、2020年から2022年というのは自分にとってどういう時期だったのだろう、この人たちはどういう存在だったのだろうと考えていたのですが、そう、光だったんです。この「光」という言葉にようやくたどり着けました。
写真を見に来てくれて一緒にきゃあきゃあしたお客さん方にとっても、もしかしたら光だったのかもしれない。私たちは同じ光に助けられていたのかもしれない。
これからも落語家という仕事を選んだ人たちを撮り続けていく所存です。あの時期の「光」とはニュアンスが違っていくのかもしれませんがきっと、これからも私にとってなんらかの光としてそこに在り続けるのだろうと予感しています。