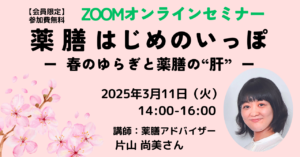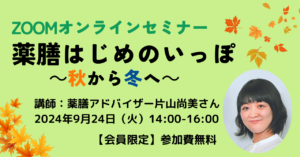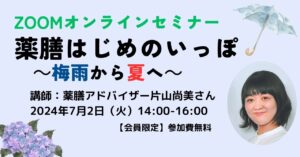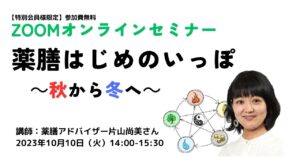皆さん、こんにちは!
常識に捉われないアイデアと大胆な行動力を持つ「世界を明るく照らす稀な人」を追いかけて東奔西走、稀人ハンターの川内です。
都内では、春の気配を感じる暖かさになってきましたが、皆さんのお住いのエリアはいかがでしょうか? 春になると、旅に出たくなる方も多いと思います(僕はいつでも旅に出たいのですが(笑))。これから旅行を計画するとして、どこで、なにをするのか、事前に検討しますよね。
やっぱり、桜は見たい。プラスアルファで、なにかユニークな体験をしたい。そう考えている方がいたら、ぜひこの記事を参考にしてほしい!

春には桜が咲き乱れる弘前城のお堀
日本には桜の名所と言われるところがいくつかありますが、なかでも日本屈指と評されるのが、毎年およそ200万人が訪れる、青森県弘前市にある弘前城と周囲の公園。約50種類、2600本の桜が満開になる4月下旬から5月上旬は、写真で見るだけでも圧倒される美しさです……と言っても、僕は弘前城で桜を見たことはありません(いつか行ってみたい!)。
今回、僕が紹介したいのは「プラスアルファ」のほう。弘前城で花見をした後、歩いて数分のところにある「現存する唯一の甲賀流忍者屋敷」に行ってみたらいかがでしょう? というご提案です。へ? 忍者? 興味ないし、と思われた方、いやいや、ぜひこのまま読み進めてください。きっと、驚きと発見があるはずです。
この路地に入ってきた時点で、忍者に見つかっていますよ。
その古びた木造平屋建ては、弘前城から5分ほど歩いた住宅街の一角にあります。家と家の間にある細い路地を進んだ先に、ひっそりと。その平屋建ての背後は高さ3、4メートルの斜面になっていて、まさに袋小路です。外から眺めまわしても、忍者屋敷だとわかる痕跡はありません。忍びの者の屋敷なのだから、当たり前か……。
この忍者屋敷のオーナーは、佐藤光麿さん。今も弘前市の職員として働く佐藤さんが、忍者屋敷の案内をしてくれるのです(要問合せ)。佐藤さんは忍者の末裔……ではないのですが、そのあたりのことは後述します。

忍者屋敷オーナーの佐藤さん
玄関先で、佐藤さんが「ここ、見てください」と玄関の上のほう、屋根のすぐ下を指さしていました。そこには、言われなければ絶対に気づかないレベルの小さな穴が空いています。
「見張り穴です。川内さんがこの路地に入ってきた時点で、忍者に見つかっていますよ(笑)」
それから約1時間、仕掛けだらけの忍者屋敷ツアーが始まりました。
弘前で暗躍していた実在の忍者集団

まずは、そもそもなんで弘前に忍者がいたのかという話をしましょう。戦国時代、弘前を含む津軽地方を領有した大名の津軽為信は、関ケ原の合戦(1600年)で徳川家を中心とした東軍として戦いました。その一方、東軍が負けても津軽家が存続できるように、長男の信建を石田三成率いる西軍に派遣しています。
西軍が破れた際、長男・信建は石田三成の次男、石田重成を津軽に連れ帰りました。その背景には、かつて津軽為信が領土問題で他家と揉め、秀吉から討伐対象とされかけた際に、石田三成の計らいで事なきを得たことがあります。津軽家から石田家への恩返しです。
石田三成の祖母は忍者の里として知られる甲賀出身で、三成も若かりし頃、武芸と兵法の修行のために甲賀で過ごしたと言われています。当然、甲賀忍者ともつながりがあり、次男・重成が津軽に逃れる時、警護役として甲賀忍者が同行したと考えられています。
この甲賀忍者たちの技術が津軽で脈々と受け継がれ、1669年、北海道で先住民族のアイヌが蜂起した「シャクシャインの戦い」で、幕府から出兵を命じられた津軽藩が諜報活動を行う際、忍者集団が暗躍したようです。
津軽の忍者集団はその後も、アイヌや敵対する南部藩の監視や諜報活動に従事。そして1673年、4代藩主の津軽信政が甲賀忍者の中川小隼人を江戸でスカウトし、正式に忍者集団「早道之者(はやみちのもの)」を結成したと言われています。
早道之者は、1870年(明治3年)まで活動したことがわかっている実在した忍者集団で、弘前藩の200年余りに渡る藩政が記録された『弘前藩庁日記』には、活動の一部が記録されています。また、弘前藩が残した『分限元帳』には、約60名分の名簿も確認されています。2018年には、青森県弘前市立図書館で武器の作り方やまじないの文言が記載された忍術書の原本も見つかっています。
忍者屋敷のお値段は?

現存する唯一の甲賀流忍者屋敷
佐藤さんが所有する忍者屋敷は、江戸時代に建てられ、早道之者の指導的役割を担った棟方家が所有していたことがわかっており、忍者の詰め所として使われていたとされます。
早道之者が解散した後、屋敷は普通の民家として使われていたようで、1953年にSさんが購入しました。Sさんが亡くなった後は3人の娘が遺産を相続し、長女とその夫が管理していました。
ふたりもSさんから「忍者屋敷だった」と聞いていたそうです。2016年、忍者を研究している青森大学社会学部教授の清川繁人さんに連絡して調べてもらったところ、「忍者屋敷と見てほぼ間違いなし」という結果が出ました。
滋賀県にある甲賀流忍者屋敷は忍者の子孫が建てたもので、実際に活動拠点として使われ、現存する忍者屋敷は国内唯一とみられることから、清川教授らは弘前市に文化財として保存するように求めました。しかし、住居として使われていた時代に増改築が行われたことを理由に認められませんでした。
それならこの貴重な歴史的遺産を活用しようと清川教授を中心に忍者屋敷のツアーが行われるようになったのですが、屋敷が老朽化し、維持管理に手がかかるため、所有者の三姉妹は手放すことを決意。そうして2020年5月、名乗りを上げたのが佐藤さんです。
「弘前市の公務員、弘前市民として、価値があるものは残さなきゃいけないと思ったんですよね。退職金の2000万円と貯金100万円の合計2100万円で購入しました」
佐藤さんは市役所を定年退職した後も再任用制度で働き続けているため、主に土日祝日、忍者体験会を開催しています。「忍者の衣装を着たい」というリクエストにも応じていて、一着1000円でレンタル可能です。

手裏剣を投げる佐藤さん
忍者屋敷の土間には畳が立てかけられていて、穴だらけの的が貼られています。「さあ、やってみましょう」と佐藤さんから手渡されたのは、手裏剣。手裏剣というと海の生物ヒトデのような形をしたものを思い浮かべるでしょう。それは「車剣」と呼ばれるもので、僕が手にしたのは鉄の棒の先端が尖っている「棒手裏剣」。佐藤さんはさすがに慣れていて、ドスッと鈍い音を立てて手裏剣が的に突き刺さると、ニヤリ。僕は何度か投げて、一度だけ、的に刺さりました。忍者気分が盛り上がっていきます。
驚きの仕掛けの数々
さあ、ここから忍者屋敷の内部をご案内。玄関の土間から見張り穴があったところを確認すると、人間がひとり寝転がれるような狭いスペースがあり、そこに小さな穴が! よく見ると、木材が四角に削り取られていることがわかります。これは、偶然できた穴ではない。忍者が横たわりながら、表を監視していたのでしょう。

足を乗せるとギギギギッと板がきしむ「うぐいす張り」
畳張りの居間に入ると、佐藤さんが、一部だけ板張りになっている場所を指して、「ここに乗ってください」と言いました。板の上に足を乗せると、ギギギギッと板がきしむようなけっこう大きな音が響きます。居間に入る人が、最初の一歩を踏み出す位置だけが板張りになっています。屋敷に侵入するとしたら夜の暗い時間帯だろうから、気づかずに板を踏んでしまう可能性が高い。これは、侵入者を知られるように作られた仕掛けで、「うぐいす張り」と言います。

押入れの上に登るためのわずかな隙間
さらに居間の奥の部屋に足を進めると、なんの変哲もない押し入れがあります。佐藤さんが「ここを見てください」と懐中電灯で上部に貼られた板を照らすと、痩せた人間がひとり通れるほどの隙間が空いていました。外からは見えない天袋があって、板の隙間を通って隠れられるようになっているのです。
とても狭いスペースですが、調べてみると江戸時代の日本人男性の平均身長は160センチに満たなかったそう。忍者は身体を極限まで鍛えているだろうから、体重も軽いはず。だから狭くて脆そうな隠し天袋にも身を潜めることができたのだと思います。
……こんな感じで忍者屋敷ツアーはまだまだ続くのですが、すべて書いてしまうと「ネタばれ」になってしまうので、これぐらいにしておきましょう。ひとつ言えるのは、わかりやすく楽しめる忍者のテーマパークは数あれど、忍者の凄みを感じられるのはこの忍者屋敷だけ! 屋敷のなかはかなり古びているけど、余計な手が加えられていないからこそのリアリティが感じられます。
ここに紹介していない分も含めて、屋敷の仕掛けや屋敷に遺された歴史の痕跡について教えてもらうたびにテンションが上がり、あっという間に1時間が経っていました。忍者の衣装から私服に着替えたら、江戸時代から現世に戻ってきたような気分でした。
いかがでしょう? 弘前城で花見をした後、弘前城で暗躍していた忍者集団・早道之者の忍者屋敷を訪ねる。かなりオリジナリティの高い旅になり、思い出話にも花が咲くでしょう。
稀人ハンターの旅はまだまだ続く――。
ADDRESS
弘前忍者屋敷
青森県弘前市森町12番地
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=ninja
※忍者屋敷ツアーについては、要問合せです。